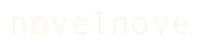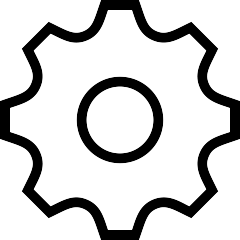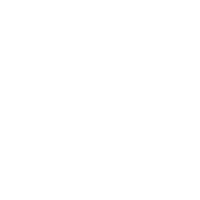近所の子供達に不名誉なあだ名をつけらた小さな橋を渡りながら、平四郎は"うんざり"という言葉について考えていた。 さて、うんざりした時に何故うんざりというのか知らん それから直ぐに"げんなり"についても考え出した。つまりはそういう気分なのである。 多江に小言をきかされた帰り道はいつもこんな調子だった。 まったくよくしゃべるひとだ きまって天気の話題から始まる叔母の小言は見合の話が主であった。
- 1 -
当の平四郎が見合いなどというものに微塵の興味も示さないのだから、それは仕方のないことだ。叔母がわずかでも如何様な思いを抱いてくれていれば、こうしてうんざりやらげんなりやらの、わけのわからぬ由来などと戯れることもないのだろう。 だがこの種の人間というものは得てして自分の価値観はこの世に等しく常識であると信じて疑わぬのだからたちが悪い。 それが親切でこそあれ、迷惑だなどとはひと時も思いはしないのだ。
- 2 -
実際、平四郎ももう数えの二十八。叔母が心配するのも当然といえば当然だ。年齢についての話は全く、平四郎の嫌いなものであるのだが。 ええい、女というものはなぜ顔を合わせた途端に俺の年と稼ぎを聞くのだ。俺はもっと別の話を…… 俺は、何について話したいのだ? 彼女らの話を邪険にするのならば、自分がそれ以上の話をしてやらねばなるまい。思えば自分は、見合の場ではいつも口を固結びにしていた。
- 3 -
互いを知るための見合いであるというのに、片方がだんまりでは進む話もないだろう。 平四郎は元々口数が多い方ではない。かといって聞き上手かというとそんなこともなく、だた相手の話の合間合間に、ああ、だの、おう、だのと相槌とも呻き声ともつかぬ音を発するのが常であった。見合いがまとまらないのも尤もである。 このまま独り老いていくのもやぶさかではない 彼女に出会ったのは、そんな風に思い始めた頃だった。
- 4 -
「儂にはもう決めた人がおる、構わんでくれ」 無論、嘘である。 平素小言などにもなにも言わない平四郎だが、この日の多江は妙にねばこく、ちくちくと嫌なところばかり刺した。 気まずくなり家を出る。 また子供に不名誉なあだ名を叫ばれたが、そんな叫びもはらい散らして、いつもの小さな橋のところまで歩く。 その時、なにかが着物の裾を引っ張ったように思った。 「あの、もし」 それは編笠を被った女性だった。
- 5 -
その女性は長い黒髪の人だった。 とても綺麗なひとでだれが見ても美人と言う言葉がお似合いだ。
- 6 -
このご時世に編笠である。 平四郎の頭に「隠密か!」というツッコミワードが浮かんだ。その刹那、 「隠密か!と思いましたよね」 女は美しい顔に微笑を浮かべ彼の心を見透かしたようなことを言う。 平四郎が困った顔をしていると、 祖母の形見ですの。 と、聞いてもないことを言う。 その表情が人懐こく、平四郎も思わずつられ笑顔を見せた。 やっと笑ってくれましたね。 女が嬉しそうに白い歯を見せた。
- 7 -
平四郎はつられた笑顔を直し、 「して、儂になにか用か?」 と尋ねた。 女はもどかしいような笑みを浮かべ、 「平四郎様に御用があって参ったのです」 と答えた。 「儂に?お主に覚えはないが…何処の者だ」 平四郎は気付かれない程度に警戒した。 「詳しくは申しませぬが、隠密の者です」 「結局隠密か!」
- 8 -
淑やかなようでいて、まぁよく喋る隠密だった。平四郎のぶっきら棒な相づちに嬉しそうに笑みを返し、そしてまた飄々と可笑しな話を放り投げてくる。 どうにも話が尽きないもんだから、女の目的なんて忘れて日が暮れるまで話し込んでしまった。来る日も来る日も、女と話すと無口な平四郎から言葉が溢れてくる。 気づけば長い年月が流れ、いつしか夫婦となった。 「あの時の用とはなんだったんだ」 「ええ、もう叶いましたわ」
- 完 -