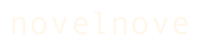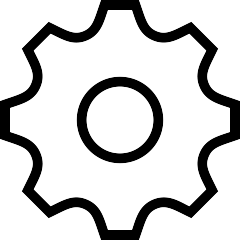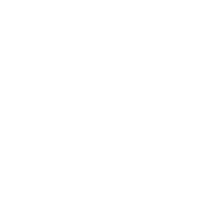静かな清流に灯篭をひとつ乗せる。輪の形に水面を揺らしたそれは、流れに逆らい山の上へ滑るように登っていった。 灯篭の中には星の欠片。淡く光を放ちながら揺れ流れ、他の光に混じり更に輝きを増す。 「今日も蒸し暑いな」 幼馴染の三紀彦がいつの間にか隣に立っていた。 「あなたも流してきたの?」 「ああ、もちろん」 山を登る光の粒々、耳を澄ますと虫の声。 山の上のその先には、夜空を流れる天の川。
- 1 -
星の欠片が込められた灯篭たちが孕む動力。その原理は不明だが、天から降りてきた星々が、再び天に還っていくのは当然の事だと、この村では信じられている。 「今年は星を探すのが大変だった」 「そうかしら?」 「わざわざ山の頂上まで行って見つけたんだ。もっと早く探せばよかった」 三紀彦はその苦労を思い出すように、眉を潜めた。
- 2 -
去年までは、幻想的な光景をただ賞でるだけだったこの行事。 だが、今年は違う。 灯篭は魂の乗り物だ。先祖や家族の魂が、星と共に天へと還るための。 三紀彦は去年の秋に、三つ違いの兄を亡くした。長雨で水の増えた川に攫われ、それきりだ。 三紀彦が星の欠片をぎりぎりまで探しに行かなかった気持ちはわかる。そして欠片がなかなか見つからなかったのも、お兄さんがまだ此方に居たいのだと訴えているように思えてしまう。
- 3 -
はて、何と言って故人と遺された魂とを慰めたものかあぐねていると、囂々とした喧騒が川下の方からのぼってきた。私達とてまだ裾野にいるのだけれど、村は更に下った先にぽつり在る。死者の魂を悼む儀には不似合いな賑やかさに、三紀彦は態度を硬くした。眉間の皺がミハル川より深く刻まれている。 「菱和の奴らだ」 東京へ出て五年で逃げ帰った菱和の三男坊である。彼は三紀彦の兄の死について、あることないこと吹聴していた。
- 4 -
「あれぇ、ウワサの弟くんじゃないか」 菱和はこちらに気づくなり、おどけた口調で吐かした。 「間抜けなお兄さんを見送りに来たのかい?でもお兄さんの乗った灯篭じゃ、途中で溺れちゃうんじゃないか?」 ゲラゲラと耳障りな哄笑。 「行こう」 三紀彦の袖を引く。灯篭を前にしていざこざを起こすのは嫌だった。 ふと菱和の手の灯篭が目についた。こんな奴にも悼むべき人がいるのかと、妙な可笑しさと同情が湧いた。
- 5 -
「あの人にも偲ぶ相手がいるのね」 「まさか。灯篭が一人でに登っていく様を面白がっているだけだろう」 三紀彦の言う通り、菱和は流した灯篭が上っていく様をニヤニヤと笑いながら携帯で撮りまくっていた。 「何してるのかしら」 「ブログに載せるんだろ。ネットじゃ、都会を捨てて、スローライフしてることになってるから」 「……いつかバチが当たりそう」 すると次の瞬間、菱和が流した灯篭が轟音と共に爆発した。
- 6 -
中に火薬でも仕込んでいたのだろう。花火にも似た光彩を夜空に残し、灯籠は流れ落ちた。菱和たちは爆発の瞬間さえカメラに収めて、喜んでいる様子だった。 「信じられない」 三紀彦の顔は紅潮して膨らんでいた。 「ほら見たか。奴にとっては遊びの道具でしかないんだ」 私は思わず三紀彦の袖を掴んだ。放っておくと、今にも飛びかかっていきそうで怖かった。 「きれい!」 事情を知らない子供のあげた歓声が聞こえてきた。
- 7 -
綺麗? どこがだ あんなのは故人への冒涜だ。 三紀彦は、そう毒づいた。 その表情はどす黒く、まるで別人だった。 「ねえ、三紀彦」 袖を、そっと引く 「…何」 「………綺麗だよ」 「お前もそんなこと言うの」 「違うよ。ねえ、上、見て」 私の言葉に、三紀彦は顔を上げた。 「あ」 山の頂上から無数の光が空へ昇っていく。 魂が、天へ還る瞬間だ。 その中に、一際輝く星がひとつ。 「…兄さん」
- 8 -
天の川に注ぐようにも見える光の筋。眩しく輝く星も、ためらうように瞬いた後、その中に紛れた。 三紀彦が息を呑む。気づけば菱和も、泣き笑いのような顔で空を見上げていた。 やっぱり菱和にも、死を悔やむ相手がいたのだろう。悲しみ方も弔い方も人それぞれだ。そしてやがては、誰もが天へと還っていく。 「さよなら、兄さん」 呟いた三紀彦は山を下り始めた。私も後を追う。 灯篭流しが終われば、村にはじきに秋が訪れる。
- 完 -