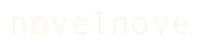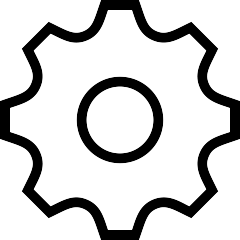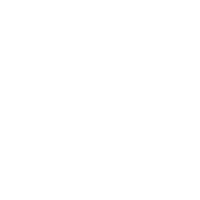【リレー小説でのマナー】 最近また、一人良かれのパラ崩しを見かけます。 2パラ以降を執筆する上で注意すべき点を皆で考えてみたいと思います。 パラを投稿する前に、1パラからしっかり読み返し内容を確認しましょう。 ■1:文体を意味なく崩さない事。 ■2:「あ、い、う、お、よ、わ」等を意味なく小文字にしない事。 ■3:意味なく句読点を無くしたり、意味なく「, 」「. 」ピリオド等にしない事。
- 1 -
■4:鉤かっこの文の最後に、句点をつけない事。 執筆者のスタイルにもよりますが、現在はこの規則が定着しております。 ちなみに夏目漱石や森鴎外など、有名な小説家の時代では逆の規則でした。 ■5:感嘆符や疑問符の使用量に注意する事。 迫力に欠けるとも思ってしまいますが、使いすぎると逆に安っぽく見えてしまいます。 また、読み手に読みづらいという印象も与えかねません。
- 2 -
■6:一人称の場合、一人称の代名詞を統一する事。 ■7:数字の表記の統一をする事。(漢数字、半角、全角数字の統一) ※気にならない人もいますし、気にする人もいます。しかし、一つの物語として読む事を考えると、表記の統一を意識する事は大事です。
- 3 -
■8:地の文の人称を変えない事。 ■9:前パラグラフで後続パラグラフ執筆者に対してのお題や縛り、ルールがあった場合は最低限それに従う事。 前述ありましたように、統一感を出す為にも必要なことです。 これが崩れると読者が違和感を覚えるだけでなく、次のパラグラフを書きにくくなる原因にもなります。
- 4 -
■10:途中のパラグラフで人称が変わっている事に気づいた場合、第一パラグラフで使われていた人称にさりげなく戻す事。 第一パラグラフで執筆者が「俺」と表現しているにもかかわらず、第二パラグラフでは「僕」になっていた場合、物語の創始者の意向を優先させます。 ただし、例えば第二〜第八パラグラフまで「僕」できてしまっている場合、流れにのって「僕」と表現しても良いこととします。
- 5 -
◼︎11:後続の人に無茶ぶりし過ぎない事。 9つのパラは、長いようで短いものです。 前パラグラフまでの登場人物や伏線を活かしつつ意外な展開を綴るのは素晴らしい事ですが、風呂敷を広げ過ぎて後続の人が書きづらくなるような内容は避けましょう。 少なくとも、自分なりに次パラグラフや結末の構想を練ってから投稿するように心がけてください。 自分の考えと違うからといって削除願いを出すのもご法度です。
- 6 -
■12:パラグラフの文字数制限をなるべく有効活用すること。 noveでは1パラにつき200字まで入力可能ですが、これは決して多くありません。 改行や句読点などでも一文字と数えるので、私も含め皆さん言葉選びや構成に苦労されると思います。 スタイルや確固たる意図がない限りは、ある程度の文字数を消費しましょう。 勿論、効果的に空白やスマホ特有の表示を有効活用している作品はこの限りではありません。
- 7 -
ー貴方がいなかったら、今の私はどうなってたんだろうか。 「俺の娘になれ」 沢山の人の視線が突き刺さる中、言われた言葉は強烈だった。何故、こんな所に、何故私が、なんてばかりが思考を巡り完全に混乱していたような気がする。 その時の私はあんなにも未熟者だったのか。 でも、あの事件とこの人のこの器のデカさ、優しさの力で今私は船に乗ることの決断ができた。 よく考えたら随分懐かしいな
- 8 -
■13:前パラグラフは反面教師とすべき具体的な例であるため、絶対に真似しない事。 手が滑った可能性もありますが、気を付けるようにしましょう。 ■14:そう警告してもやらかしてしまう人は必ずいるため、後続の人も努力を怠らない事。 具体例はこのパラです。バトンが落ちても拾う人がいれば、小説は繋がります。 ■15:以上の事項を守り、またリレー小説家としての責任を持ち、そして必ず楽しんで書く事。
- 完 -