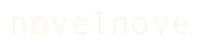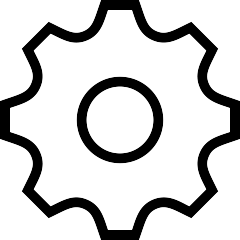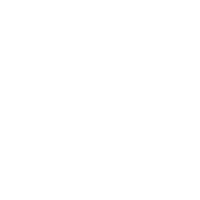夏の夜 赤子の次は ひぐらしか 以前このような俳句を読んだことがある。 しかしこの俳句は変なのだ。 "夏の夜"と言っているのにもかかわらず、"ひぐらし"と来ている。作者がもし"ひぐらし"を夏の季語だと勘違いしていならば、それで収まる。しかし、私はあえて"ひぐらし"を使ったと考えている。 誰か考察を求む
- 1 -
確かに“ひぐらし”は秋の季語である。 しかしこの句は晩夏の、まだほんのりと薄明るさも残った夕刻から夜への静けさを詠っているのではなかろうか。 気の早い羽虫の鳴き声や晩夏を静かに楽しみたい詠人の意に反して、可愛い赤子は疳の虫に泣き、やっと泣き止んだかと思えば、今度はヒグラシが鳴き始めた。詠人は苦笑いしかながらも、我家の変わらぬ日常と、ヒグラシの鳴く夜を楽しんでいる。この句からはそんな情景を感じる。
- 2 -
悲しく解釈してみよう。 夜の次には朝がある。「次は」と続くくらいだから、移り変わる日を考えても悪くない。 「次」は未来のことである。 赤子の未来と言い換えることができ、ヒグラシに続く。 「か」に感嘆文のニュアンスを取り入れる。 以上から、 早くも、夏が終わり、秋が訪れようとしている。赤子は必死に夜泣きしているが、薄命である。季節の移り変わりが早いように、病弱な赤子の余命も日ごと減っていく。
- 3 -
単純なあたいはこれを文字通りに読んだ。 舞台は、夕日泥んで風もそよそよ吹き始めた夏の終わり。清楚なよなよ系女性が縁側に自分の赤ちゃんをだいてちょこんと座っている。赤い着物に黒い帯。うちわ。多分シングルマザー。そんなおなごの汗ばんだ肌と着物の隙間をやはりそよ風がさらっていく。 さあ問題はひぐらしだ。前のお二人が妙絶なので不勉強なあたいは出番がない。 ただ赤子は母に見守られてひっそりと成長する気がする
- 4 -
赤子は、今は夏の夜に存在感があるが、次は日暮らしに存在感を増す。乳飲み子が成長し日に日に活動時間が伸びてきている様子を、子育ての楽しみと苦しみを両方含んだ俳句だと思いました。 俳人にとっては、ご近所さんにも赤子がいらして、一人泣けば二人三人とシンクロし合唱する泣き声に、ひぐらしの美しくも悲しげな鳴き声を重ね合わせ、蒸し暑い夏の夜のBGMとして聴き耽っているんだと思いました。
- 5 -
赤児とひぐらしの二重奏が、ふいに止む。赤児が泣き疲れて眠りについたのだ。続いてひぐらしも、鳴き止んだ。夏の夕暮れに静寂が訪れる。 ひぐらしも眠りに落ちたのだろうか? いいや違う、命が尽きたのだ。ひぐらしは今、死んでしまった。ぽとりと死骸が地面に落ちた。 真っ赤な夏の夕陽は、ひぐらしの最期の命の灯だった。 一匹の蝉の命が消え、夏の夜は徐々に暮れていく。 赤児は静かに眠っている。
- 6 -
歌人の中でも特に個性派の面々が集まる俳句クラブ「high cool」。日々居酒屋に集まっては、勉強会という名目でくだを巻いている。 さて本日の会合の建前は「夏の夜 赤子の次は ひぐらしか」なる俳句の批評であった。 とはいえ、所謂己が一番の烏合の衆、勝手な言い分を言い散らすのみだ。その内、誰かが酔いに任せて言い始めた。 「これでは埒が明かぬ。この句の真意、一つこっくりさんに尋ねようではないか」
- 7 -
酔った勢いもあり、やろうやろうと皆が言うのだが、僕はコックリさんの恐ろしさを知っているため、頑なに拒否した。 「なんだか、意気地がないんだね。あんた」 僕にそう言い捨てて、コックリさんを始め出した。 「夏の夜 赤子の次は ひぐらしか」の意味を教えてちょーだい。と、誰かが言うと十円玉がススっと動いた。 ウヘェと僕は目を丸くするがみんながそれを読み上げていく。 「これは、6ぱらのひとがせいかいじゃね?
- 8 -
「誰そいつ?」 「え、あいつだよほらあの〜…あれ?そんな奴いたっけ?」 「だから知らねーって」 何それ、怖いと騒ぎが大きくなってきた時、 「コックリさんだよ」 え。その場に不気味な静けさが訪れる。 「皆で呼んだじゃないか」 急に存在があやふやになる人間がいる。粗方人外なのだ。 「はじめまして、はおかしいか。名前はそうだな…」 ヒグラシ アカコに決めた。 夏の夜の夢や怪しき
- 完 -