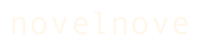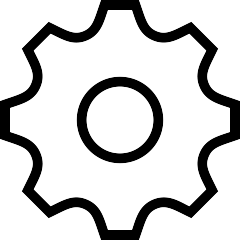「私、夏を食べてしまった」 夜中に彼女が起き上がり、突然こんなことを言い出した。 どんなに扇風機を向けても、息が詰まりそうなほど寝苦しい夜だった。きっと悪い夢を見たのだろう。冷たい麦茶を汲んできて、震える彼女に飲ませてやる。 「大丈夫、今もこんなに暑いんだから」 彼女は小さく頷いて、再び布団に潜り込んだ。 翌朝、彼女はどこにもいなかった。 妙に薄ら寒い部屋で、扇風機だけがはたはたと回っていた。
- 1 -
彼女が眠っていた布団が湿っている。寝汗というよりも体中の水分が溶け出たのかというくらいに。 夏を食べた彼女は、夏に溶かされたのだろうか。 彼女の異様な震えから感じた恐怖がそんな非現実的な思考に行き着いた。 ひとまず、彼女の友人たちに行方を訊ねたが、皆口を揃えて知らないと言う。彼女の両親にも訪ねようと思ったが連絡先を知らない。 携帯を持たず消えた彼女は、一週間経っても見つからない。
- 2 -
そして、このところ巷を苦しめていた猛暑も、彼女の失踪とともに鳴りを潜めてしまった。 大暑を過ぎたばかりというのに、最高気温が二十五度を下回る日が続き、ほとんど秋の様相だ。過ごしやすいと周囲が喜ぶ中、気が気ではなかった。 たとえ溶かされたのだとしても、飲み込み飲み込まれるウロボロスのように、夏は彼女の中にあり、彼女もまた夏の中にいるはずだ。 けれど夏が消え去るなら、きっと彼女も永遠に戻らない。
- 3 -
あの日から洗濯しないまま置いてあるシーツ。彼女の痕に触れると、もう殆ど乾いてしまっていた。 寝ている間に何が起きたのか。知る必要があった。彼女との約束を破ることになるけれど仕方ない。彼女が遺して行った携帯を開く。SNSのアカウントに自動ログインしてみた。何のことはない日常に混じって、〝恋人〟のことがちらほら。それは今どうでも良い。夏──夏に関する言及を探す。その時、別のアプリからの通知が届いた。
- 4 -
それは、アルバムアプリだった。 新規更新を告げるアイコンを、震える指先でタップする。 目に飛び込んで来たのは、数枚の写真。緑濃い山奥、目映い海岸線、陽炎立ち上る夕焼け。いずれも、真夏を切り取る美しい風景ばかり。 彼女の携帯はここにあるのに、どこからログインしたのか。 ただわかることは、彼女は夏と共にまだ生きているということだ。 居ても立っても居られず、彼女の携帯を片手に外へ飛び出した。
- 5 -
何十枚とある写真を見て気づいた。あの景色には見覚えがある。 よく散歩した近所の森、君が「綺麗だね」って笑ってた海辺、彼女のお気に入りの展望台。 確かに彼女がいたという痕跡を探すように、ただがむしゃらに走り回った。 どれほど美しい景色が切り取られていても彼女はいない。 彼女はいないのに、その夏らしい景色の中に確かに彼女の存在を感じるのだ。 「夏を食べたって言うなら、君から夏を吐きださせないとね」
- 6 -
向かったのは、近所の森からそれほど離れていないところにある河川だった。 散歩の帰り道に立ち寄って、活き活きとした鮎が泳ぎ回っているのを二人で眺めた。 通知音が鳴り、リアルタイムにアルバムが更新される。1分前の表示、岩を割って飛沫をあげる清流の写真があった。強い日差しを反射する川の煌めきは、目の前の光景と乖離していた。 「迎えに来たぞ。そこにいるんだろう?」 君に届くよう、大きく声をあげた。
- 7 -
その刹那、 ばしゃんと水飛沫が上がった。 それと同時に辺りを蒸し暑い空気が包む。 「…来て、くれたの」 姿は見えないが、声が聞こえる 「当たり前だろ」 ああ、お前、やっぱりそこにいるんだな。 「でも、もう、だめよ」 「何を根拠に」 「夏を、食べてしまったもの」 「吐き出せばいい」 「無理よ」 厚く、熱く、暑い空気を、抱きしめる。 「無理じゃない、帰ろう」 だって、お前、ここまで案内してくれただろ?
- 8 -
更に強く抱きしめようとして、自分に腕がないと気づいた。体もなかった。いつしか変化していたのだ。記憶も甦り、全ての因を悟った。 「私が気づかなければ人のままでいられたのに」 彼女が囁く。 だから消えたのか。恋人こそが夏だという秘密を食べたまま。 「苦しめてごめん」 「今度こそ私を貴方の中に溶かして」 駄目だ。そう言おうとした。だが遅い。 辺りにはもう何の気配もなく、眩しい夏の日だけが照りつけていた。
- 完 -