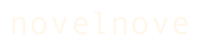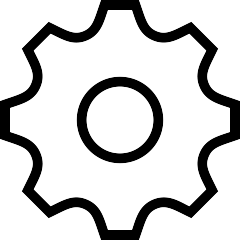シトロンのドロップは少し甘すぎた。去年までは、この季節の風にぴったりだと思えていたのに何故だろう。 「髪が伸びたね。切りに行く暇がないのかい」 隣で貴方が首を傾げている。 「それに少し痩せたみたいだ。もしかして、何か悩みでもあるのかな」 そうか。こんな相手にはきっと、目の覚めるような青い飴玉がいいんだ。 ラリマー、トパーズ、アクアマリン。 大人のくせにミントが苦手な貴方に、ソーダ味だよと嘘をつく。
- 1 -
「青空も、きっとこのくらい爽やかな味なんだろうね」 貴方はアクアマリンを美味しそうに頬張って、微笑んだ。 去年までは、すぐに吐き出すくらい毛嫌いしていたくせに。貴方も、変わってしまったの? 私もアクアマリンを舐めてみたけど、物足りなくて、トパーズも一緒に食べてみる。 やっぱり、夏にはサファイアのほうが好きだ。 長年、宝石飴屋を営んできた私だ。知識量には自信はあったけれど、修行をしなくちゃ。
- 2 -
宝石飴屋の始まりは祖父母。見た目も美しい宝石のような飴で、戦後貧しさに喘ぐ人々の心を潤したいという願いから宝石飴の移動販売を始めたのだと聞いている。 代々譲り受けた宝石飴のレシピ帳には美しい色を出す為の水飴と着色料の分量が書かれている。 ちなみにレシピ帳はもう一冊ある。元々ガラス職人だった祖父が編み出した宝石飴の独特のカット方法を記したもので、祖母のレシピ帳と対に私が引き継ぐはずだったものだ。
- 3 -
祖父のノートを受け継いだのは妹の方だった。宝石飴の光沢を際だたせるために編み出されたカッティング技術は、今は別のものに応用しているらしい。 私たち姉妹は小さい頃から一つのものを取り合ってきた。祖母の作ったダイアの宝石飴を取り合って大喧嘩したことは、今でも家族の話のネタになっている。 「昨日、君の妹さんと出会ったよ」 アクアマリンの包み紙をくるくる縒って、彼はなんでもないように言った。
- 4 -
「店に行ったの?」 妹は、祖父の技術で氷を削っている。 初めは芸術家として名を馳せたが、今は名門レストランで働いている。 「違うよ。昨日昼に入った洋食屋で、たまたまな。」 「昨日のお昼?店はどうしたの?」 「知らないよ。」彼は優しく笑った。 「気になるなら、連絡をとってみればいい。」 妹とは、いつからか疎遠になっていた。 …ううん、本当はいつからか分かってる。 彼を取り合ったあの日から。
- 5 -
彼はジュエリーバイヤーだ。ふらりと海外に飛んでは、原石を仕入れて帰ってくる。彼の目利きが確かなことは、私の首元を飾るアレキサンドライトのネックレスが証明している。 「たまにはかき氷でも食べに行こうよ。ブルーハワイなんてどう」 「あんなの甘いだけ」 最後にお眼鏡にかなったのは私。でも、彼は時々こうして意地悪を言う。 丸くなった飴にがりり、と歯を立てた。アクアマリンとトパーズが、口の中で混ざり合う。
- 6 -
すぅ……と冷えた喉元から吐き出す言葉は、やはりカキリ、かたくなる。勝ったのは私のはずなのに、どうしてか今も敗北感に似たものを、紅く静かな心臓の裏に育てている。罪悪感、だろうか。 「お互いたった一人の姉妹なのにね」 彼は家族と言うものに夢を見過ぎている。近過ぎると、全てが倍々に膨らんでしまう。 「いいけど、私、氷は白蜜しか食べないの」 シンプルなタンブルに成形した宝石飴達を一握り、鞄に忍ばせた。
- 7 -
《フラッペ》と書かれた看板の店の前に、見覚えのあるイヤリングの女。 「仲直りしよう」なんて罪深い言葉を、彼は吐いた。いつもの意地悪?それとも、本心? 「良かったら、どうぞ」 私が差し出したタンブルを一瞥して、女は笑った。 「サファイアが無いじゃない。ああ、売り切れか。夏は人気だもんね」 冷ややかな笑みは、アクアマリンのよう。鋭く美しく、カットされていて。 「ダイアが無いのも、その所為かな?」
- 8 -
ぐさぐさと心を刺す悪意に唇を噛んで堪える。そして鞄からアクアマリンのタンブルを取り出した。 「何よ」 「あなたならこの石の意味が分かるでしょう」 「……仲直り?」 「仲直りするつもりはないわ。でももう奪い合うのは嫌。終わりにしたいの」 そう言って、タンブルを握らせる。そして呆気に取られる妹に背を向けた。 これで終わり、これでいい。 嬉しそうに走ってきた彼が軽く背中を叩いてくれた。
- 完 -