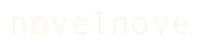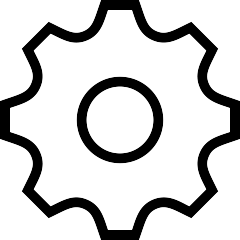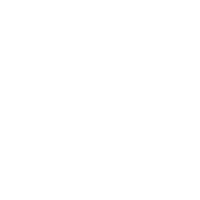最近、リレー小説というものにハマっているのだが、僕が書き込むとそこでリレーが途切れてしまう。「いいね」の評価も一つも付かない。 まあ、評価に媚びて文章を書くつもりも無いのだが、反応が全く無いのも些か寂しい。 ここは一つ「いいね」が付く文章の書き方というのを考えてみようと思う。 まず大切な事は、
- 1 -
文を、よく読むことだ。 他のユーザーの記述をよく読む。最低でも3回…いや、5回は読む。 前の文と矛盾しないためにはよく読んでよくわからなければいけない。矛盾すると後の人も困ってしまう。 そして、何度も読むことで以前のパラグラフを執筆したユーザーが書きたいのはどんなことか、どういう話の拡がりを期待しているかを察するのだ。 その中で、無理のない自分なりの展開を生み出す。 次に心がけているのは…
- 2 -
「起承転結」だ。使い古された手法だが、やはり物語には、読みやすいバランスというものがある。 はじめの2段落くらいは「起」で、読者の関心をひく「つかみ」が必要だろう。この部分は世界観の説明も兼ねている。 続く2、3段落の「承」では前段までを踏まえ、ストーリーを順当に展開していく。「起」で提示された世界観から大きく外れることはしない。読者はようやくこの世界に慣れてきたばかりなのだ。
- 3 -
それに続くのはテンポだと考える。無駄に一文を長くするとか、句読点を増やして、さもそれっぽく見せ掛けるのは素人特有の小手先のこすいやり方だ。 要は決められた字数で簡潔さ&完結さを上手く表現しなければならない。 きっと多くの、この手の小説を書いている人間の悩みは語彙ではないだろうか。 自分とて才に恵まれているとは自負していない。 それでも次のシーンに滞りなく流れさせる努力はする。 そのためにも、
- 4 -
日頃からの読書は欠かせない。自分自身も「書く側」の人間となると、読書に対する姿勢も自然と変わってくる。セリフのつなげ方、場面や心情の描写、ストーリー展開。ただ読んでいただけの頃と比べると、読書という体験から学べることは格段に増えていることに気づくはずだ。 おっと、脱線してしまった。起承転結の話題に戻ろう。
- 5 -
「転」。ここが重要だ。 リレー小説は短い。短い中で物語をちゃんと終わらせるには、物語の中盤で話を終盤に向かわせる変化、すなわち転が必要不可欠なのだ。 転の内容は、次の筆者が繋げやすい、終わりに向かいやすいものが理想的だ。 つまり、終わらせる準備をする、というのが転なのだ。 これが無いがために話の終着点を見つけられず、止まったままのリレー小説を数多く見てきた。 次の書き手のことを考えて書こう。
- 6 -
自分なら残りの節をこのように書く、というイメージを立てた上で執筆するのも良い。自分が終わらせられない話を人に託すなど、とんでもないことである。もちろん、思い通りの結末に行き着かないところもリレー小説の醍醐味なので、不確定な要素をいくつか残しておくことも忘れないように。できあがった世界の中で、物語を大きく展開させる「転」部の執筆は比較的難易度が高いと言える。 では、物語の締め「結」の解説に移ろう。
- 7 -
「結」ーーー。 これで物語の良し悪しが決まってしまう、といっても過言では無いだろう。そしてやはり、ここでも大変な作業がある。 およそ7人から8人の文章に残された要素を拾っていかなければいけない。書く際には誰よりも前の文章を読み返さなければいけない。どの場面よりも根気が必要だろう。 さて、ここまで「起承転結」について解説してきたが、リレー小説でなにより大切なものがある。 そう、書き手の「心」だ。
- 8 -
つまりはシンプルだが、「作品を大事にしよう」という気持ちである。これを一人一人持ち合わせていれば、自然と物語は紡がれてゆき、素敵な作品が出来上がることだろう。 このパラグラフを以てこの話は終結してしまう。けれど、僕が今リレー小説に抱いている考えは全てここに記したつもりだ。 もしこれに共感を覚えたならば、次に執筆する物語に活かしてもらいたい。 それだけがここまで綴った僕…いや"僕ら"の望みだ。
- 完 -